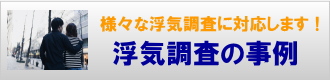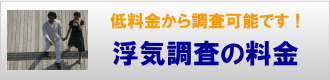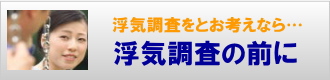離婚には、「協議離婚」、「調停離婚」、
「審判離婚」、「裁判離婚」の4通りの方法があり、
日本国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。
離婚には、「協議離婚」、「調停離婚」、
「審判離婚」、「裁判離婚」の4通りの方法があり、
日本国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。
夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。
話し合いにより離婚に合意できない場合は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。
また、夫婦間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、調停前置主義により、すぐに裁判をすることはできませんので、
協議できない場合は、まず調停となります。
ほとんどの方は協議離婚です
協議離婚とは、夫婦二人の合意と、役所への離婚届提出ですべてが済んでしまう離婚のことで、日本で離婚する夫婦の約90%は「協議離婚」ですが、 一方が離婚に同意しなかったり、親権や養育費、慰謝料など金銭的な条件で揉めたりしますと、裁判所が入る離婚の手続きに進みます。裁判所が関わる離婚
裁判所が入る離婚は、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の三つで、どの場合においても、まず家庭裁判所で離婚調停を受けることになり、 離婚全体の割合の協議離婚の90%を引いた残り10%は、ほとんどがこの段階で分かれる「調停離婚」になることが多いようです。それでも夫婦の意見がまとまらないときは、地方裁判所で離婚裁判をすることになり、 その判決(場合によっては高等裁判所や最高裁判所)によって離婚が成立するのが「裁判離婚」です。
稀に調停で合意できなかった時点で、家庭裁判所が独自の判断で離婚を宣言する事があり、これを「審判離婚」と言い、 この宣言に一方が不服だった場合は、裁判へと進みます。
協議離婚
協議離婚とは、別れる理由は何でもよく、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。・ 離婚意思、離婚届提出、受付で協議離婚は成立します
・ 離婚届を出すこと
・ 未成年の子供がいる場合は、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する事
なお、親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれませんので、親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなり、 その他、慰謝料の額・財産分与の方法などで意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様です。
また、不貞問題や金銭絡みなどで、不利な調停や裁判をきらい、 どちらか一方が協議も何もしていないのに勝手に離婚届を提出してしまうというような事例が見受けられますので、 事前に揉めそうな予感があるような場合は、役所の窓口に離婚届不受理申出書を出しておくという場合もあります。
離婚のほとんど90%は、この協議離婚といわれています。




 離婚を有利に進めるにあたって、もしも配偶者に不貞の影があるような状況であれば、浮気調査をおススメします。
離婚を有利に進めるにあたって、もしも配偶者に不貞の影があるような状況であれば、浮気調査をおススメします。